
先の衆議院選挙でもそうでしたが、八王子に深い縁も無い、八王子のために働こうという意志も無い、八王子に骨をうずめようという気もない人が、八王子の選挙区に来て、ここからこの地域の代表(=私たち住民の代表!)として国会議員になろうとする行為に対して、私のような住民は、あなたが想像できないほどの深い心痛をおぼえ、ずっと、ずっと、気が気でない精神状態に置かれることを、一度でもいいから考えてみて下さい。
それは未知の侵略者(または横暴な外国人)がやって来て、郷土を奪われる、という感覚にも似たもの(→ 否、保守の流儀では同じ出来事)でして、どうか私の心からの叫びとして、この選挙区に来ないようにお願いします。また先の衆院選のような事態が起こるのは大迷惑です。でも、もしそうなったのなら、私は、萩生田ピカ一議員をとことん応援し尽くします。!!
自民党…どころか日本をぶっ壊した小泉元総理でさえ、「刺客」は地元出身者から選ぶように努めたと言いますし、そうでなくては地元民はバカバカしくなって、投票率はどんどん下がることでしょう。
ですから、八王子とは縁の無かった(関西出身の)あなたが抱えるトラブルや問題意識は、是非、別の次元や手法で解決して下さい。
裁判でも、リコール運動でも、出版でも、ネット言論でも、なんでもあるでしょう。…… あわよくば、国会議員になれて、地元民の上に立てる「選挙」だけは、やめてください。
まるで記録映画の「紅衛兵」みたいなヒステリックな演説。本当に、
参政党は、こんな人を党の候補者として公認するのですか?……
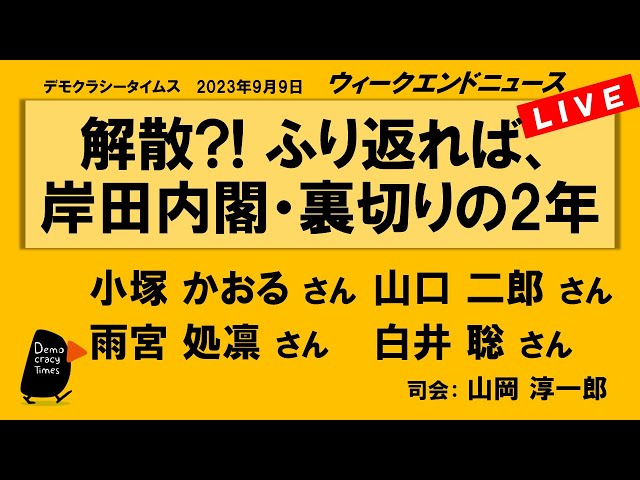
(※写真は「DJ学問ラジオ」様より)
こういう事が度重なると、地域の一有権者として素朴に思うのは、その地域で選ぶのが「国会議員」なのですから、立候補者には、最低でも、その選挙区内での5年くらいの「居住経験」を義務付けるべきではないのか……とも思えて来て、政党の候補者選びにとっては都合が悪そうですが、そう感じざるをえない状況です。!!…
で、この人、本当に「紅衛兵」なのかも……と思えて来る動画もあって、好き嫌いはございましょうが、ご参考までに。→【朝香豊の日本再興チャンネル】萩生田事務所が告訴するのは当たり前 内乱罪になるわけがない
※ ※ ※
.jpg)
いつもどおり!に、「化けの皮」がはがれるのが早過ぎる、小泉進次郎。
※ ※ ※
※ ※ ※
※ ※ ※
.jpg)
さて、気を落ち着けて本題の方に入りますと、前回の記事では「黒い板張りの層塔型天守」が出現した原因として、「望楼型から層塔型へ」「黒い天守から白い天守へ」という天守の変遷が、実は、食い違いのように、ズレて進行していたからかもしれない、との勝手な推測を申し上げたわけですが、かねてより当サイトではさらに…
・多聞山城をはじめ、文献や絵画史料で“外壁の色”が確認できる初期の天守は、どれもこれも白壁ばかり、という意外な事実があること。
・そして慶長2年の木幡山伏見城天守こそ黒い五重天守の始まりで、その直後から黒い岡山城天守や広島城天守などが続いたに違いない。
・しかしその一方で、松本城天守の度重なる改築・増築の歴史を振り返れば、慶長2年以前にも黒い三重天守などは存在した可能性があり、その変遷は天守画イラストに描いた。
と申し上げて来ていて、これらは自分でも整理できていない感がありましたので、そこを反省して、全体を網羅する時系列の略図を作ってみました。
(改訂版)
.jpg)
といった感じで、天守の「黒い白い」等々の変遷を考えているところですが、ただ、この図の詳細については、次回に改めて、具体例を挙げつつ申し上げたいと思っておりまして、今回のブログ記事は、久しぶりの完全な「番外編」としまして、日本のバブル崩壊は、実際には米国の圧力で崩壊させられた!対日政策なのか―――という強い疑いについて、あえて申し上げてみたいと思うのです。
と申しますのも………
【 失われた30年…による「五公五民」という戦後最低の政治 】
「税金が安いのはいいことだ。しかし、今の社会保障を担保するためには、消費税を下げた分をどこに財源を求めるのかという話がないと辻褄が合わない」「私はそういう政治をしてはいけないと思う」
.jpg)
いま世間で影の総理と言われる森山裕(もりやま ひろし)自民党幹事長の、つい先日の発言ですが、この説明のしかたは、財務官僚がよく政治家に吹き込んできた詐術の一種!…であるということは、すでにかなりの国民の方々がご承知の事柄でしょう。
(→ そもそも税の取り過ぎ状態。物価高で消費税収も大幅増。しかも使い切れなかった予算の意図的?な多さ。プライマリーバランスを言う国は他にない異常性。単年度主義一本槍の財源論。実際は国債を増発しているのに赤字国債を完全否定する。税収弾性値の意図的な操作。社会保障費をからめたステルス増税の横行。などなど
→ →「五公五民」という戦後最低の政治 )
では今さら、影の総理が何故、こういう見え透いた話をしてまで、断固として消費税「減税」に反対するのか―――と言えば、それは必ずしも知識が乏しいからではなくて、実は、父親が南朝鮮出身のほぼ在日二世のこの政治家自身にとって、
<< 減税阻止が、この先の「権力」維持のための「絶対条件」だからである >>
という重大な観点を見逃すことは出来ません。!!
森山裕の権力の源泉とは、間違いなく自民・公明両党が先の総選挙の惨敗で「少数与党」におちいったからこそ、のものであって、つまり森山自身の長い国対委員長の経験による<<野党との太いパイプ>>が、少数与党の石破政権をかろうじて運営する命綱(いのちづな)になっているため、とりわけ石破総理は、森山裕の言うことにまったく逆らえない!という状況が生じています。
そしてこの影の総理が、この先の「権力」維持のため、「次の手」として考えているのが、夏の参院選で自民党が大きく議席を減らすのは間違いない情勢ですので、参院選後に(石破総理を見限って立憲の野田佳彦を新総理に立てるか否かは別として)いずれにしても、ますます少数与党をうまく舵取りする必要性が極まるわけで、そこであわよくば、
<<財務省が喜ぶ増税路線の、自民+立憲+維新+公明?の与野党「大連立」>>
に持ち込めれば、そこでは自分がなおも、大連立を裏でつなぐ「絶対的な影の総理」として君臨できる!!―――との思惑が、森山裕の心の底でたぎっているのは間違いなく、いま減税などをして、増税路線の大連立が遠のくのは、ぜんぜん嬉しくない!のです。

かくして、ほぼ在日二世の男なのに、現代の藤原道長か、「闇将軍」田中角栄の再来か、というウソのような事態……いや、もっとひどい状況にもなりうるのは、左翼政党・立憲の野田佳彦や安住淳が、これにどっぷりと加担する可能性があるためで、もしそうなれば「異論」を出せる場は極端に限られましょうし、新総理の野田佳彦もまた「森山裕のロボット化」するのは必然!!の運命(=第二政党から出る総理だから)でしょう。
ですから例えば、週刊文春の石破「闇」献金疑惑についても、これは実は、森山裕が国税庁≒財務省と結託して、石破が減税に流れないように、石破をおどすためのハッタリ(怪事件)ではないのか?…という気もしておりまして、実に恐ろしい事態が政界中枢で進行中のようです。
で、そういう風に、自らの「権力」維持のためならば、豊かであった国民がだんだん疲弊して、どんなに苦しむ状況におちいっても構わない、といった政治姿勢は、あの、チャウシェスク大統領の時代の悲惨なルーマニアを、私なんぞは連想してしまうのですが、いかがでしょうか。
銃殺の4日前に、共産党建物から演説するニコラエ・チャウシェスク
( 憲法の改正による終身大統領 / 1989年12月21日の最後の演説 )
.jpg)
Murim mai bine in lupta cu glorie deplina decat sclavi.
奴隷として死ぬより、栄光のうちに戦場で死ぬ方がましだ。
東欧ルーマニアのチャウシェスク大統領は、1965年から80年代にかけて念願の工業国化を果たしたものの、次第に対外債務の返済に追われるようになり、その際、プライドの高さのせいか、欧米に対して債務の軽減を交渉するよりも、国内の超「緊縮財政」で債務を完済する道を選んだため、国民生活は急激に悪化し、とうとう1989年春に「ルーマニアは対外債務を完済した」と晴れやかに宣言したものの、その年末の国民の暴動・決起による政変で(夫妻ともども)銃殺刑になった人です。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
そして一方、失われた30年を経た我が国・日本では、十代~二十代の方は全員が、かつての勢いにあふれた闊達(かったつ)な日本社会を全く知らないのだ……と思うと、この際は、今回のテーマのようなブログを書いて、森山裕やチャウシェスクとはまるで意味のちがう「悪人?」を取り上げてみたいと思った次第なのです。
.jpg)
< 番外編。バブル全盛期の「信用創造」パワーに米国はおののいた。
信用創造の考え方では、BIS規制後の「貸しはがし」こそ
日本の自傷的「貨幣破壊」だった >
かつて「バブル四天王」の一人とされた、イ・アイ・イ(EIE)インターナショナルの社長・高橋治則(たかはし はるのり/1945―2005)
.jpg)
さて、ご覧の(1995年の国会証人尋問の写真の)高橋治則という人は、全盛時には「環太平洋のリゾート王」「南海のリゾート王」などと呼ばれて、自家用ジェット機で時に大蔵官僚を接待旅行で同乗させつつ、太平洋を縦横に飛んでリゾート投資を大々的に行った人物として、その容貌などが人々の記憶に残っています。
そこで彼の全盛時、1991年末の時点でEIEインターナショナルが保有していた主なリゾート等を、写真(一部CG)でザザザッとご覧いただきますと…
<※( )内は当時の購入金額 / ただしリージェント・ニューヨークは新築 >
サンクチュアリー・コーブ(豪/612億円)
.jpg)
ブリタニック・ハウス(英/607億円)
.jpg)
虎ノ門ビル(港区/389億円)
.jpg)
ボンドセンター(香港/409億円)現リッポーセンター
.jpg)
リージェント・シドニー(豪/389億円)現フォーシーズンズ・シドニー
.jpg)
リージェント・ニューヨーク(米/289億円)現フォーシーズンズ・ニューヨーク
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
リージェント・ビバリーウィルシャーホテル(米/274億円)
.jpg)
フエフエ・ラーンチ(ハワイ/242億円)

.jpg)
ボンド大学(豪/209億円)
.jpg)
ヒルクレスト・ゴルフクラブ(栃木/197億円)
.jpg)
!!…… と、これらの物件をご覧になって、城郭ファン、とりわけ石垣ファンの皆様なら、あれっ…とお感じになるものがありませんか。
特に高橋がニューヨークに「新築」したリージェント・ニューヨークの出来栄えを見ますと、これらは高橋が、何の審美眼もなく、やみくもに超高額な不動産を買いあさった結果、というわけでは全くなかった……という(強欲な経済事件の被告人のまま急死した人にしては?)かなり意外な一面を、私なんぞは感じざるをえないのですが、いかがでしょう。
当時の高橋の自宅(現スーダン大使館)
.jpg)
先ほど、とりわけ石垣ファンの皆様ならば…と申し上げたのは、この高橋の自宅を見ていただいても、彼の好みというか、選択の判断基準のようなものが見えて来る気がしまして、それもそのはず、高橋はなんと旧平戸藩士(あの松浦氏の家臣!)の家系だそうで、生まれは終戦の年、疎開先の平戸だったとのこと。
(平戸市HPより)
.jpg)
平戸城に行かれた方はご存じでしょうが、湾を囲んで瓦屋根の家並みがずらっと広がりつつ、その中に教会建築が印象的に建っている土地柄で、これが高橋のバックボーンとすればその「好み」はうなずけましょう。
さらに高橋は昭和初期の“ライオン宰相”濱口雄幸の遠縁にあたり、その濱口の次男が長銀の二代目頭取という関係はあったものの、バブル以前の高橋自身は、3M商品などを扱う従業員100名弱のコンピュータ関連の販売会社の社長に過ぎませんでした。
.jpg)
で、そんな高橋がにわかに「環太平洋のリゾート王」と呼ばれ始めたのは1986年、たまたまハワイの高級ホテル、ハイアット・サイパン(現マリアナビーチリゾート)が売りに出ている情報を得て、それを長銀(かの杉浦敏介が頭取だった頃の日本長期信用銀行)に打診したところ、EIE本社ビルを担保に12億円の融資が得られ、そうした長銀の信用力を背景にハイアット・サイパンを購入したこと(購入額42億円)でした。
長銀はその頃、顧客の大企業が新株発行による資金調達に移り始めたのを横目に、新たな貸出し先を開拓する必要に迫られていて、一方でEIEは海外からの投資情報が舞い込む立場になっていたため、EIEは長銀からの融資でリゾート投資を急拡大させた結果、その後のわずか5年間で!…総資産額を6068億円に伸ばし、グループ企業を加えた総資産額は1兆円に達したと言います。
しかし高橋自身は「5年計画でアジア太平洋に10兆円のリゾート地帯をつくりたい」と周囲に語っていたらしく、まだまだ道半ば…だったようですが、このように高橋自身は国内で“地上げ”をしたわけでもなく、資産として現物の不動産を海外でかき集めていた(に過ぎない?)人物でした。
したがって高橋は、地価高騰が目に余ったバブル景気において、国内の不動産価格を不当に釣り上げたわけではなく、長銀の杉浦頭取が「信用創造」でじゃんじゃん融資してくれるのに乗っかって、主に海外で買いまくった立場でしたから、追加融資に次ぐ追加融資の状態では、個々の不動産の収支や値上がりがそこそこの水準であれば経営上の問題は無く、最終的には、それら海外資産の代物弁済によるEIEの計画的な倒産と、その後の別会社での転身……くらいの逃げ道は(杉浦頭取と共に)考えていたのではなかったでしょうか。
――― ですから結局のところ、高橋という人は、悪人には違いないものの、日本人全体にとって“特段の害悪”をもたらした人物でもなかったのに、この直後に、運命が暗転しました。 → いわゆるバブル崩壊(想定外の信用収縮!)へ。
ここで私なんぞが思うのは、もし高橋に対する批判的な感情があるとすれば、それは長銀の莫大な融資について「それはきっと、我々預金者の預金が、高橋だけに不公平にまわされたのだろう」といった、
<<「信用創造」に対する完ぺきな誤解!! >>
によるものの可能性が高いだけに、ここはハッキリさせておかなくてはいけない、と感じるのです。
<「信用創造」credit creation とは、
銀行が、預金者から集めた預金とは桁違いのレベルまで、
銀行自身が判断する融資(貸し付け)によって、
一瞬にして、預金通貨を「創造できる」仕組みのこと >
イングランド銀行 本店(ロンドン)
.jpg)
世界の銀行が業務として行っている「信用創造」については、イングランド銀行のホームページにある「Money creation in the modern economy(現代経済における貨幣創造)」の中に、こんな風に書かれていて、万年筆マネーとも言われる「信用創造」が端的に説明されています。
In the modern economy, most money takes the form of bank deposits. But how those bank deposits are created is often misunderstood: the principal way is through commercial banks making loans. Whenever a bank makes a loan, it simultaneously creates a matching deposit in the borrower’s bank account, thereby creating new money. The reality of how money is created today differs from the description found in some economics textbooks: Rather than banks receiving deposits when households save and then lending them out, bank lending creates deposits.
(翻訳)
現代経済では、ほとんどの貨幣が銀行預金という形をとっている。しかし、銀行預金がどのようにして作られるかは、しばしば誤解されている。
主な方法は、商業銀行が融資を行うことである。銀行が融資を行う際には、必ず借り手の銀行口座にそれと同額の預金が作られ、それによって新たなマネーが生み出される。
今日、お金がどのようにつくられているかという現実は、経済学の教科書に載っているような記述とは異なっている。銀行が家計の貯蓄から預金を受け取り、それを貸し出しするのではなく 、銀行の貸し出しそのものが預金を生み出すのである。
ということでして、この「信用創造」による潤沢な銀行融資は、投資銀行が様々に発達した欧米では、日本ほどには企業経営(業容拡大)の頼みの綱とはならなかったものの、終戦時に焼け野原から再スタートした日本経済にとっては、欠くことの出来なかった手法であり、そこから驚異的な高度経済成長や国際的な競争力も実現できたのだと言って構わないのでしょう。
【 そして破局の前夜へ 】
1988年、ついに日本の銀行は、世界の銀行の「総資産ランキング」で25位以内のうちの17行を占めて、世界の半分以上をになう圧倒的な地位に至った―――
.jpg)
この表を改めて見直しますと、これはとどのつまり、日本の各銀行が長年にわたって「信用創造(貨幣創造)」で生み出して来たものが、まさしく「資産」に他ならなかったのだと、欧米がはっきり認めた結果でもあることに留意すべきでしょう。
とにかく「信用創造」はケインズやシュンペーターも認めた銀行業務であるだけに、この時、こういう日本の一人勝ちの快進撃を止めるためには、「信用創造」そのものを否定するのではなく、例えば銀行の自己資本比率の引き上げ(=融資の総額に対する銀行の自己資本の比率を4%から8%へ)といった“ルール変更”によって、他国の側は反撃するしかなかったわけです。
これは自己資本比率がたまたま!約8%だったアメリカの商業銀行には、なんの影響も無かったものの、それまで4%としていた日本の各銀行にとっては、8%に引き上げることは青天の霹靂(へきれき)であり、これを達成するには、どこかの支援を受けて自己資本を「倍に」増資するか、これまでの融資の総額を「半分に減らしてしまう」=顧客からの無慈悲な「貸しはがし」しか手はありませんでした。
そしてこの「貸しはがし」は、信用創造の考え方で言えば、融資が返済された瞬間に、生み出された預金貨幣(資産)は消滅する仕組みですから、「貸しはがし」は取りも直さず、銀行が自らの資産を自傷的に打ち消す「貨幣破壊」であって、それこそ日本の銀行を「世界の総資産ランキング」から、一気に、叩き出してしまえる魔法の手だったのです。
国際決済銀行(BIS/スイスのバーゼルにある本部)

そんな自己資本比率の引き上げ、という新ルールを打ち出すべく、にわかに動き出したのが「バーゼル銀行監督委員会」でした。
それ(the Basel Committee on Bank Supervision/BCBS)は国際決済銀行のなかに事務局を設けた、G10諸国の中央銀行総裁が集まる「委員会」に過ぎないものの、1988年、国際決済を行う世界中の銀行に向けて、自己資本比率8%を義務づける!勧告としての「バーゼル合意」Basel I(→ 日本国内ではBIS規制という言い方が一般的)を策定したのです。
そしてここに興味深い一枚の写真があります。 中央の右側の人物は誰でしょう。

この写真は問題の「バーゼル合意」の6年後、1994年9月の国際決済銀行(BIS)の取締役会の記念写真ですが、中央の右側に写っている人物は、誰あろう、退任直前の、三重野康(みえの やすし)日銀総裁です。
バブル期に地価高騰と闘う姿が「平成の鬼平」と
マスコミにもてはやされた、三重野日銀総裁
.jpg)
(※ご覧の三重野は、日銀はえぬきで、1984年の副総裁就任から長く日銀の事実上の最高実力者でした。もともとプラザ合意後の内需拡大の掛け声によって続く金利引き下げには反対であり、あの株価が最高値の1989年12月に!新総裁に就任すると矢継ぎ早の金融引締め策を実施しました。 そしてバブル崩壊で傷んだ経済下でも、なおも引締めを続ける…という失敗を犯したとされます)
――― で、まことに残念ながら「バーゼル合意」Basel I がどういう風に策定されたのか、そこに大蔵省や日銀・三重野がどう関与したのか、という詳細はブラックボックスの中のようで、よく分からないものの、上記の記念写真から「推理する」ならば、おそらくは上記のBIS会議場で、1988年の時点で、
<< 日銀総裁は自己資本比率「8%」を受け入れていた >>
と想像するしかなく、つまりは、当時の株価の最高値3万8915円をつけた89年の年末には、実はその前年に、すでに日銀総裁が(世界や米国の圧力に負けて)その後のバブル崩壊(膨大な信用収縮と貸しはがし)や失われた10年・20年・30年に至る道を、自ら選択していたのだ!?……という悲惨な実態が見えて来そうなのです。
.jpg)

日本経済新聞より
今から思えば、ならばあの時、(三重野が必死のSOSを発して?)日本政府がいっせいに各銀行に対して4%→8%分の「資本注入」をしてしまえば良かったじゃないか、と、悔しい思いにもなるわけですが、それは住専問題ひとつでオロオロしていた(→ 銀行だけを助けるのか!という世間の声にあらがえなかった)政治家を思えば、それも無理な注文かもしれません。
しかも当時、銀行業界の側にも、政府による資本注入には強いアレルギーがあったそうで、それは国民感情への配慮や、強制的な半国有化を嫌ったから、という理由よりも、ひょっとすると、現在の「国債」論議から想像すれば、「信用創造」というものを感覚的にまるで受け付けない“役人根性”への警戒感が、すべての銀行マンの心の底にあったからではないか……とも感じるのですが、いかがでしょう。
※当サイトはリンクフリーです。
※本日もご覧いただき、ありがとう御座いました。

.jpg)