ついに、日本に、その日がやって来てしまった……
あの李完用(り かんよう/写真右)は晩年に言った。「75年後には日本に李姓の総理大臣が出るだろう」と。
.jpg)
そして現在、自民党の森山裕幹事長(写真左)はなんと、父親が南朝鮮出身の、ほぼ在日二世のような人物だという。 まるで責任感の無いイシバ政権は事実上、「森山政権だ」と言う声が世間に多々あり、ならば、安倍元総理の死から3年もたたずして、日本は、どこまで変わり果てるのだろうか。
→ → 選択的夫婦別姓で自民党議員に党議拘束をかける、と公言している森山裕には、確かに日本国籍はあるのだろうが、きっと、転がり込んだ権力を使って、日本の伝統文化を破壊できることが、嬉(うれ)しくて嬉しくて、たまらないのだろう。
※ ※ ※
※ ※ ※
※ ※ ※
美濃金山城 犬山城 福知山城
.jpg)
さて、前回の記事<年頭別談>では、ラストの近くでこんな一文を「追記」させていただきました。
(※追記→ 現状の犬山城天守は、他の古い様式の望楼型天守に比べて、望楼部分が「やや過大(頭でっかち)」に感じるのは、私だけのことでしょうか?…… )
これをご覧にならなかった方々には突然で恐縮ですが、この件は今や、個人的な感覚による「放言」では済まされない話になって来ているようで(→ 望楼型の丸岡城天守が<実は寛永期の建造!>と判明して以降、それがホットな話題であり続けているためですが)一度、きちっと申し上げた方がいいのかも、と思い直しまして、これを「前回追記の弁明」として申し上げてみたいと思います。
< 現状の犬山城天守は、他の古い望楼型天守に比べると、
望楼部分がやや過大=頭でっかち?か…… >
で、私が感じた疑問とは、
< 犬山城天守は、最上階屋根の向きが初重・二重目の屋根と直交する「前期望楼型天守」の姿なのに、それにしては望楼部分がやや過大=頭でっかちに感じる >
ということでして、これは結局、「望楼型って何?」という、古くて、新しい問題に関わって来るようです。
犬山城天守のドローン写真(サイト「犬山観光ナビ」様からの画像引用)
.jpg)
思えば「前期望楼型」とか「後期望楼型」といった説明を盛んにされていたのは、内藤昌先生であったと思いますが、いま改めて、先生の著書『城の日本史』から「天守の様式」という分類を要約して抜き書きしますと…
前期望楼型天守 安土城・岡山城・宇土城(熊本城へ移建)など
後期望楼型天守 萩城・彦根城・姫路城など
前期層塔型天守 亀山城・小倉城・名古屋城など
後期層塔型天守 元和度江戸城・福山城・寛永度二条城など
復古型天守 犬山城・高知城・松山城など
という風に「五つ」に分類されていて、なんと…犬山城天守は「復古型」に分類されていたのですね。(失念)
しかしこれらは、その後の調査の結果、例えば後期望楼型(=最上階がやや大きくなったために、その屋根の向きが初重等の入母屋屋根と同じ向きに変わったもの)に含まれる丸岡城天守が、実は、ずっと後の後期層塔型と同じ寛永年間の建造であったと判明し…
さらに犬山城天守は、最上階屋根が「前期望楼型」の形であるとおりに、部材の年代測定の結果でも、豊臣政権下の織田信雄の時代に下層から上層まで同時期に創建されたと判定されて、どこが「復古型」なのか?…という風に、今は天守の様式をめぐる“静かな大混乱”が起きていると申せましょう。
ちなみに、内藤先生の分類では「前期望楼型」の中に「宇土城(熊本城へ移建)」を含めておられ、これは熊本城の宇土櫓のことでしょうが、犬山城と同じ三重天守の形になっているのに、最上階は他の五重の!前期望楼型天守と同じ「3間四方」に仕立てられていて、つまり内藤先生が挙げた前期望楼型は、どれも、3間四方で統一されていたことになります。
(※ただし当サイトは持論として、豊臣秀吉時代の大坂城天守や肥前名護屋城天守は、丈間や京間の「2間四方」であったと申し上げて来ておりますし、また熊本城の大天守は、後に取り込まれた入側縁を含めれば「5間四方」となります)
ところが、その一方で……
再び犬山城天守の望遠レンズ写真(サイト「犬山観光ナビ」様からの画像引用)
.jpg)
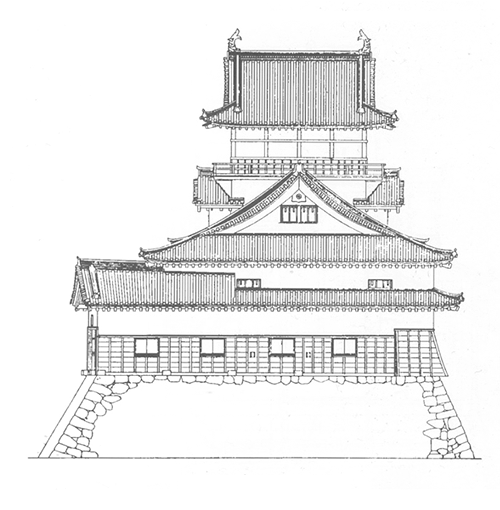
という風に、犬山城天守の望楼は「柱割で3間×4間」実寸で3間半×4間という長方形の、しかも建物全体の長短とは直交する!長方形の平面になっていて、これは天守の類いで言うなら、熊本城の小天守の「3間×5間」くらいしか類似例の無い、けっこう特殊なプロポーションであって、それだけ建物の平側に“顔を突き出した”ような望楼であるとも申せましょう。
!――― この事こそ、私なんぞが、
< 犬山城天守は……望楼部分がやや過大=頭でっかちに感じる >
という感覚の具体的な原因か?とも思えて来るのですが、そういう意味では、最上階が建物全体に直交する「3間×4間」と言えば、かつては沼城天守だった…との伝承がある岡山城の大納戸櫓が、まったく同じ発想の「3間×4間」であったことに思い至ります。
岡山城の大納戸櫓
.jpg)
(考証・作図=石井正明)
.jpg)
.jpg)
そしてさらに、同じく「建物の平側に“顔を突き出した”ような最上階」として挙げられるのが、福山城の伏見櫓の「4間×4間」や、津山城の備中櫓の「4間×4間」でありまして、これらの大櫓は、平側の壁面が初重の壁面と同一の「面」になるほど“顔を突き出して”いて、同じ発想の建て方だったと申せましょう。
福山城の伏見櫓(写真左)
.jpg)
(※ご覧の写真は、読売新聞社「美術展ナビ」様からの画像引用です)
津山城の備中櫓(復元)
.jpg)
(※ご覧の写真は、旅館「季譜の里(きふのさと)」様のHPからの画像引用です)
さてさて、こうなりますと、
< 犬山城天守の……頭でっかちに感じる >
という現象には、けっこう奥深い背景があったようにも思えて来まして、これらは何故こういうデザインになったか?と申せば、それは、これらの大櫓が建っていた場所(=城内での位置づけ)に答えがあるはずでしょう。
上記写真でもおおよそはご推察いただけるとおり、これらは、それぞれの城内で、大手門から中枢部に至る要所で<印象的に立ちはだかる!><登城者や敵兵を威圧的に見下ろす!>という、まったく同じ位置づけや役割を担っていたと思われ、そこで試しに、犬山城天守と並べて比較いたしますと…
犬山城天守 岡山城の大納戸櫓
.jpg)
.jpg)
という風に、犬山城天守というのは、構造的に申せば、大納戸櫓や伏見櫓、備中櫓とほぼ同じ規模、しかも“顔を突き出した最上階”を持った建物であり、その独特の最上階をそのまま!高く望楼として立ち上げることで「天守」になったのが犬山城天守……といった理解も可能なのかもしれません。
ですから、ちょっと言葉が過ぎたら恐縮ですが、小笠原氏や成瀬氏の尾張藩の附家老という立場を踏まえて強弁すれば、江戸時代の犬山城天守というのは、言わば尾張藩にとっての「要所で印象的に立ちはだかる大櫓!」の体をなしていたのではなかったのか?……… とさえ思えるのですが、どうなのでしょう。
< 天守の望楼型と層塔型は、江戸時代においては、
(技術的な条件ではなく)大名の「格式」で選択されたのではないか
と指摘する、中尾七重先生の、実に大胆で鋭角的な問題提起。>
( 一昨年4月の講演会ポスターからの抜粋 )
.jpg)
さて、突然ですが、ここで是非ともご紹介しておきたいのが、ネット上にPDFが公開されている中尾七重先生の論文『江戸期天守と大名支配 : 城絵図に描かれた天守の形状』であり、この論文で中尾先生は、前述の天守様式をめぐる“静かな大混乱”を収拾できる方策を模索しておられます。
(上記論文より)
これまで天守形状を技術発達と関連付け、元和以降には層塔型天守が建築されるとしたため、丸岡城天守が寛永年間の建築と判明した時、層塔型が主流となった寛永期になぜ丸岡城天守が望楼型で建築されたのか、という戸惑いがあった。
しかし望楼型と層塔型の天守も石垣も技術的に異なるところは無い。 しかも望楼型天守が慶長期以前に限られるという前提が崩れている。 寛永期と判明した丸岡城の望楼型天守を正しく城郭史に位置付けるためには、「未発達な天守構造」と「天守台の不整形」と「望楼型」と「慶長年間」を結び付ける考え方を再考し、江戸幕府の大名支配における望楼型と層塔型の天守格式の意味を理解する必要がある。
という風に、中尾先生は天守研究のやや危機的な状況(揺れる天守様式の位置づけ)に対して、それを救う処方箋を示したい、との問題意識から、積極果敢な指摘をされたのだろうと思うのですが、先生の具体策の要点をまとめてみれば…
<< 江戸時代、天守の外観(望楼型か層塔型か)は、幕府の大名統制の手段として使われていて、どういう外観かは大名の「格式」に合わせられ、時には大名格式の上昇・下降に応じて、天守は江戸時代にも外観を修正し続けていたのである >>
という、実に大胆で、鋭角的な論述をされておられます。
ただ、私なんぞの印象では、このPDF論文の中だけでは検証例がやや少ないように感じましたし、結果論で申せば、例えば姫路城や彦根城や岡崎城の天守は、江戸時代の二百数十年の間に(すっかり譜代大名の城として定着したのですから)なぜ「望楼型→層塔型」と修正(改築)されなかったのか??…といったギモンも感じなくはありません。
ですが今後、もっと多くの検証例の検討が進めば、中尾先生のおっしゃるように、江戸時代に望楼型が選択された場合の、れっきとした根拠や法則が見えて来るのかもしれませんし、そうなれば「尾張藩にとっての要所で印象的に立ちはだかる大櫓!」など申した強弁にも、何らかの言い分が見出せるのかもしれず、今後の成り行きを見守りたいと思います。
(美濃金山城 犬山城 福知山城)
.jpg)
それでは最後に、前回も申し上げた金山越(かねやまごし)の真相として、もしも「天守」望楼だけが「そのまま移築」になっていた場合のことを、申し添えておきましょう。
なぜ当時の犬山城主・小笠原吉次は、美濃金山城の「3間×4間」の望楼を是非ともそのまま使いたい!と考えたのか? → そこには政治的・経済的な動機よりも、もっと“物理的な動機”が強くあったのかもしれない、と感じるからです。
その動機とは、美濃金山城天守も、犬山城天守も、ともに
<< 断崖絶壁の極(きわ)に建っていたから >>
なのではないでしょうか。(→ つまり前述の「大櫓」と同じ条件下になる。)
犬山城の場合

(※この写真はサイト「楽天トラベルガイド」様からの画像引用です)
前回記事より。 赤い楕円 → 美濃金山城天守の正しい位置?
.jpg)
いかがでしょうか。……………
※当サイトはリンクフリーです。
※本日もご覧いただき、ありがとう御座いました。

.jpg)